ピラティスは、”ゆらぎ世代”の弱りつつある体幹を整えるのにとてもおすすめのエクササイズです。

ピラティスにも流派があって、ストットピラティスという流派がおすすめらしい・・・
どんな理由で、おすすめなのかしら?
という方のために、ストットピラティスについてわかりやすく解説していきます



この記事最後までお読みいただきますと、ストットピラティスが”ゆらぎ世代”にぴったりのエクササイズであることがわかります。
ストットピラティスの誕生背景とは?
〜ジョセフ・ピラティスのクラシカルスタイルからの進化〜
ストットピラティスは、カナダ出身の元ダンサーであるモイラ・メリットューと、スポーツ医学の専門家ジョン・メリットューによって開発されました。
1980年代後半、ピラティスがダンサーやセレブの間で注目されはじめた頃、クラシカル・ピラティスの動きに現代の医学的知見を加え、より安全で効果的なエクササイズに改良しようという思いから誕生したのがストットピラティスす。
当時のクラシカル・ピラティスは、ジョセフ・ピラティスの教えを忠実に守っており、動きの精度は高いものの、個々の体の違いや姿勢のクセに対応する柔軟性には欠けている部分もありました。
そこで、モイラは自身のリハビリ経験をもとに、身体構造や筋骨格系の正しいアライメントに注目し、「誰でも無理なく、安全に行えるピラティス」を追求。理学療法士やスポーツトレーナーと連携しながら、医学的な裏付けを持った新たなスタイルを作り上げたのです。
元ダンサーとスポーツ医学の専門家のクラシカル・ピラティスの動きに現代の医学的知見を加え、より安全で効果的なエクササイズに改良しようという思いから誕生した



誕生の秘話からしても、からだに優しいエクササイズであることがわかりますね。
ストットピラティスの基本原則:美しい動きは、正しい基礎から


ストットピラティスは、身体の構造に基づいて設計されたモダンピラティスの代表格。特に大切にされているのが、次の6つの「基本原則」です。
これらを意識することで、ただやみくもに動くのではなく、効果のあるピラティスを行うことができます。



それぞれについて詳しく見ていきましょう!
① 呼吸(Breathing)
ストットピラティスでは「胸式ラテラル呼吸」と呼ばれる横隔膜を使った呼吸が基本です。
肋骨の左右と背中側に空気を送ることで、体幹が安定し、動作中に深いコアの筋肉(特に腹横筋)を活性化できます。呼吸を意識することで動きにリズムが生まれ、集中力が高まります。
② 骨盤の配置(Pelvic Placement)
骨盤は、動作の起点となる重要なパーツです。ニュートラル(自然なアーチを保った状態)とインプリント(骨盤を少し後傾させ腰を床に近づける)の2つの配置を使い分けながら、安定した体幹の支えをつくります。骨盤の正しい位置が、腰痛予防にもつながります。
③ 胸郭の配置(Rib Cage Placement)
呼吸に連動して動きやすい胸郭(肋骨)ですが、肋骨が前に突き出すと腰や背中に余分な負担がかかります。常に肋骨を骨盤の上にそっと乗せるようなイメージで保つことで、姿勢が整い体幹の安定性が増します。
④ 肩甲骨の動きと安定性(Scapular Movement and Stability)
肩甲骨は腕の動きをサポートする重要な部分ですが、不安定なまま動かすと肩こりや首の緊張の原因に。ストットピラティスでは、肩甲骨の滑らかな可動と安定性のバランスを重視し、優雅な上半身の動きを引き出します。
⑤ 頭と頸部の配置(Head and Cervical Placement)
頭の位置が前に出ると、首や肩の緊張を引き起こします。エロンゲーション(引き上げ)を意識し、頭頂を天井方向に伸ばすように配置することで、背骨全体が整い、呼吸もしやすくなります。
⑥下肢のアライメント(Lower Limb Alignment)
足首・膝・股関節が一直線になるように整えることで、体重のバランスが安定し下半身の筋肉を正しく使えるようになります。特に膝に負担がかからない安全な動作には、このアライメントの意識が欠かせません。
今まで、あまり意識せずになんとなくエクササイズをしていた方は、ぜひこの6つを意識して、取り組んでみてくださいね。
ストットピラティスは、マットでもマシンでもできる柔軟なエクササイズ構成
ストットピラティスは、マット(フロア)で行うエクササイズと、リフォーマーなどの専用マシンを使ったエクササイズの両方に対応しています。
そのため、スタジオでも自宅でも、自分の生活や体力に合わせて無理なく始めることができるのが特徴です。



以下に、二つの特徴をわかりやすく表にまとめてみましたので、じっくりご覧になってくださいね。
マット vs マシンの比較表(ストットピラティス)
| 項目 | マットピラティス | マシンピラティス |
|---|---|---|
| 使用道具 | ヨガマット・クッションなど | リフォーマー・キャデラック・チェアなどの専用マシン |
| 負荷の調整 | 自重(体重)を使う | バネ(スプリング)で負荷やサポートを調整可能 |
| エクササイズの幅 | 初心者~中級向け 基礎を習得しやすい | 柔軟性・筋力に応じた細やかな調整が可能 |
| 関節への負担 | 正しいフォームであれば少なめ | より間接にやさしく、安全性が高い |
| 持ち運び・手軽さ | 自宅でも気軽に取り組める | スタジオや設備のある場所が必要 |
| 向いてる人 | 初心者、運動習慣をつけたい人、在宅で取り組みたい人 | インストーラに指導のもと、適切に腰痛・肩こり・姿勢改善をしたい人 |
表のとおりマットでは、体重を活かした基本的な動きを中心に、インナーマッスルをじっくり鍛えることができます。
一方、マシンではスプリング(バネ)のサポートや抵抗を使って、より精密で効果的な動きをサポートします。特にリフォーマーは、関節にやさしく、リハビリや慢性痛を抱える方にも人気があります。
ストットピラティスの認定制度とは?


ストットピラティスは、世界的に信頼されているピラティスメソッドのひとつです。その質の高さと安全性を維持するために、しっかりとした指導者認定制度が整えられています。
認定の特徴
- Merrithew(メリセュー)社が運営
ストットピラティスの認定制度は、カナダのMerrithew社が公式に管理・認定を行っています。世界中の教育機関と提携し、高水準の教育を提供しています。 - 段階的なカリキュラム
認定は、マット(Matwork)から始まり、リフォーマーやキャデラックなどのマシンピラティスまで段階的に学べる仕組み。基礎から応用まで、実践的かつ安全性の高い内容が組まれています。 - 実技と理論のバランス
解剖学や生体力学をベースにした知識に加えて、実際のクラス指導スキルや評価試験も重視され、バランスよく学べる点が特徴です。
認定取得の流れ(例)
- **初級〜中級マットコース(IMP)**の受講
- 実習・見学・指導練習時間の確保
- 実技・筆記試験に合格
- 必要に応じて、リフォーマー・キャデラック等のマシンコースを追加受講
信頼される資格として
ストットピラティスの資格は、国内外のスタジオで高く評価されている資格のひとつ。身体に不調を抱えるクライアントにも対応できるよう、理学療法や解剖学の要素も大切にしています。
まとめ:”ストットピラティス”がおすすめな理由


ストットピラティスは、”ゆらぎ世代”の不安定な心身にやさしく寄り添う、現代的なピラティスということがおわかりいただけたかと思います。
クラシカルピラティスのようなハードなフォームや筋トレ要素は抑えられていているので、運動能力が落ちて不安なかたでも安心です.
そして、ストットピラティスは、「リハビリの考え方に基づいた、やさしく丁寧なアプローチが特徴」なので、骨盤や背骨の自然な位置を大切にしながら、無理なく体幹を整えることができます。
呼吸や姿勢も意識しながら、自律神経を整え、疲れやすさや不調の軽減にもなります。



ゆらぎ世代は、日々体調が異なるので、自分のペースに合った”ストットピラティス”は長く続けられるとてもよいエクササイズだという結論です♡
ぜひあなたの生活に”ストットピラティス”を取り入れてみてください




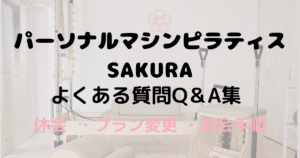



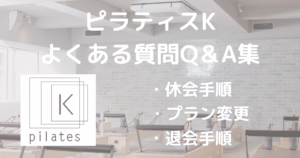
コメント